目次 ▼
クラウドソーシングを上手く活用するには
先日、コワーキングスペース茅場町 Co-Edoで開催された、クラウドソーシング有効活用 #1「クラウドワークスを使った開発手法」なるイベントでお話させていただく機会がありました。
クラウドソーシング大手「クラウドワークス」を使って開発している方のノウハウを活用するための勉強会です。
クラウドソーシングサービスを使っている方、これから使おうと検討している方、発注者・受注者さまざまな方が総勢30名以上集まる活気あるイベントでした。

そのイベントを通して、改めて考えたクラウドソーシングの課題や今後を話したいと思います。まずはイベントの説明から。
「クラウドワークスを使った開発手法」イベント概要
クラウドソーシング有効活用 #1「クラウドワークスを使った開発手法」
クラウドソーシングを活用するためのノウハウ・Tips等を共有し、より効率的にビジネスしていくための経営者や開発者向け勉強会です。
イベントページ(もちろん終了済み)
クラウドワークスを使った開発手法
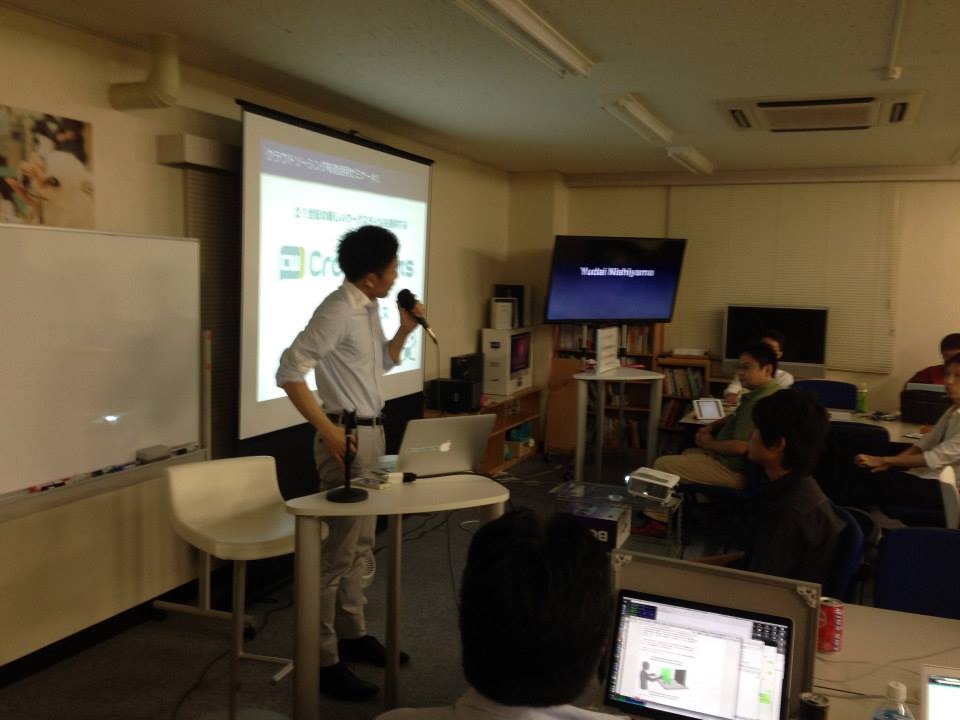
まず、クラウドワークス西山さんが登壇されました。
「クラウドワークス」の概要や実際の案件事例などかなり突っ込んで面白いお話が聞けました。
今後も定期的にセミナーや、おもしろイベントを開催していくようです。
後日談ですが、西山さんいわく
ユーザー、または潜在ユーザーと非常に近い距離でお話させて頂いて、非常によかったです。特に、ユーザーから直接改善要望やヒントをもらえるところがありがたかったですし、非対面で完結できるサービスだからこそ、対面でのみなさんの肌感覚みたいのを常に意識して、サービス運営にあたりたいです。
とのこと。
100%失敗しないクラウドソーシングの発注方法
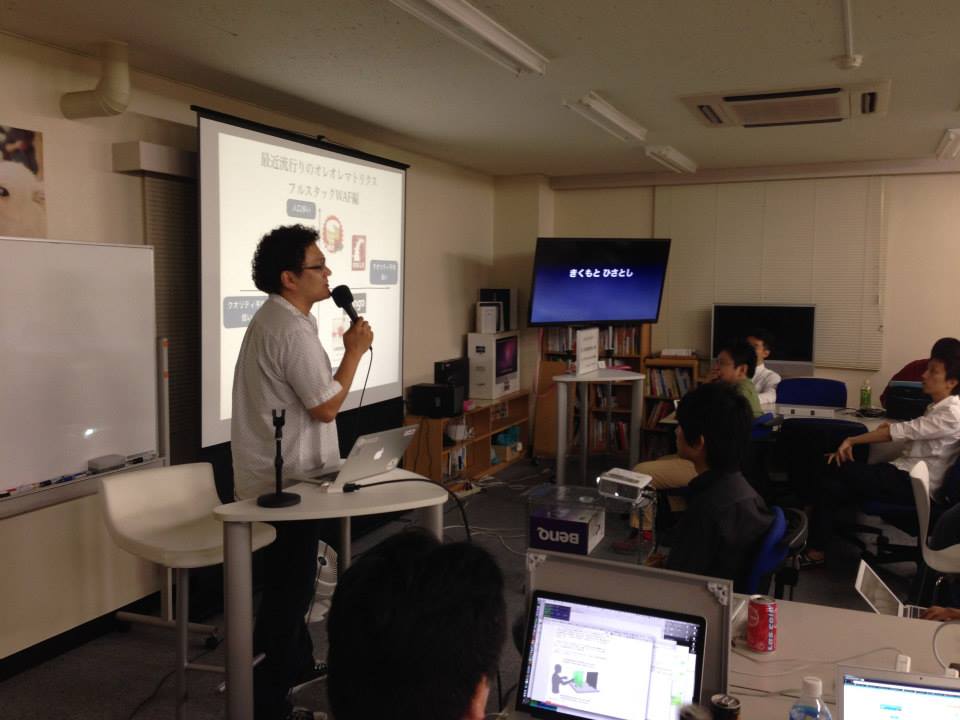
続いてポケットメニュー菊本さん。
自社サービスポケットコンシェルジュは社内リソースを一切かけず、クラウドワークスの時給制でエンジニアを募集して継続的に開発を進行しているとのこと。
言語選定から開発フロー、注意すべき点など、「100%失敗しない」というだけあって、その活用方法はかなり細かい所まで考慮されているし、リスクヘッジがされているなと感じました。
クラウドソーシングの発注者は受注者のどこを見る?発注者にとってのリスクヘッジとは
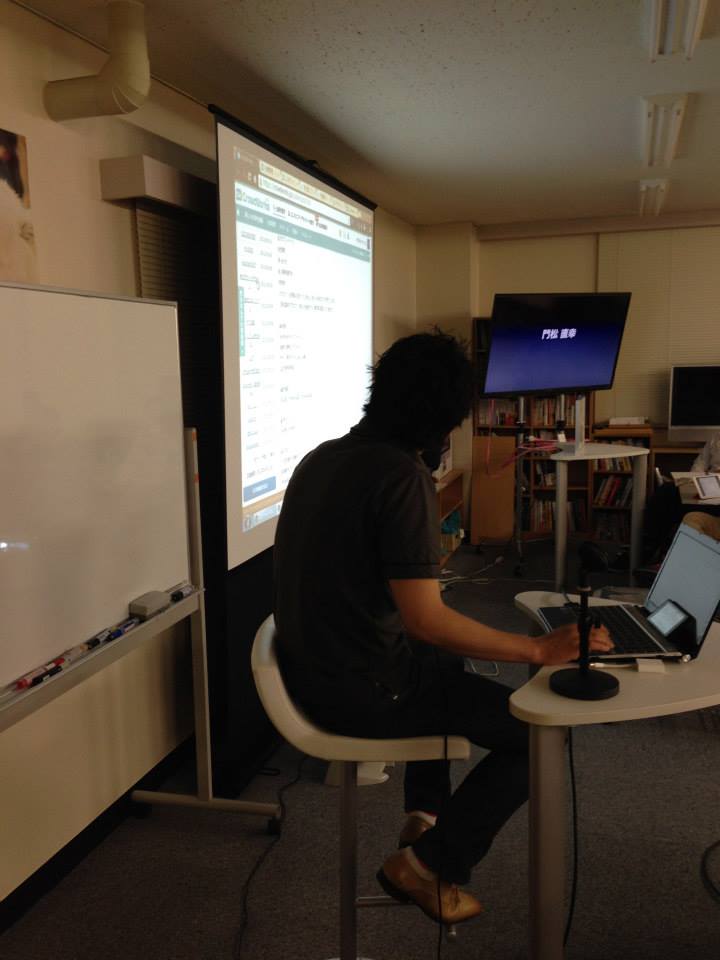
最後に私、門松が登壇しました。
サイクスとしてもクラウドワークスは、サービスローンチ当初から利用しています。
クラウドワークスを利用していく過程でもいろいろなPDCAがあって、実際に過去発注した案件を例にエピソードを交えて話をさせていただきました。
・ 依頼をする時の注意点は?
・ 良い仕事をするためには良いエンジニアと結ばれなければいけない。良いエンジニアを探すためにはどうするか?
・ どうやってリスクヘッジするか?
総括すると、前段の菊本さんがお話されている内容と非常に似通っていたので、これが現状のクラウドソーシングサービス活用方法として最善の解である、ということを改めて認識することができました。
クラウドソーシングの課題点
恐らく、クラウドソーシングを活用する上で一番難しいのは、発注者と受注者の意思の疎通です。
クラウドソーシングは「場所を選ばない仕事のスタイルを提供するサービス」であるため、沖縄の人が発注者で、北海道の人が依頼者ということも考えられます。
実際に何らかの業務を円滑に進めるためには、会うことが一番わかりやすいのですが、そのようなわけにもいきません。
中でも、システム開発が絡んでくる案件は他のジャンルよりも、意思の疎通が取りづらいと考えています。
それは、デザインやライティングなどに比べて、案件自体の粒度が大きくなる上に、完成までの手段やその手段による金額に、違いがでる可能性が高いためです。
そしてさらに、それらを擦り合わせるための方法自体が、業界のルールとして決まっていません。
もちろん、この課題はシステム開発だけではありませんが、粒度が大きくなりやすいシステム開発は、課題が顕在化しやすいはずです。
・案件の粒度が大きい場合に、少人数でこなすことが難しい
・難易度が高い業務ほど上記の問題が起きやすい
クラウドソーシングにおけるシステム開発の流れ
システム開発と一言で言っても、以下のとおりいろいろなジャンルがあります。
・ Webサイト製作
・ 業務システム開発
・ アプリ開発
・ これらに付随するデザイン製作
・ これらに付随するインフラ構築
…etc
あるシステムを作りたい人がいて、その依頼を受けてつくる人がいます。
“こんなものを作りたい”、”こうなるように動いて欲しい”、といった外部仕様を提示して、システムが作られます。つくる人は、社内にいる人かもしれませんし、外部の開発会社かもしれません。
いずれにしても、作りたい人が必ずしもシステム開発を理解しているか、というとそんなことはないでしょう。理解していないケースの方が多いと思います。
そういった場合、みなさんが開発会社だとしたら、どのように納品フェーズまで進行させるのでしょうか。
1. 要件定義:もしくはRFPをもらって、工数算出して、見積り提出。
↓
2. 開発/製作:合意したら、開発に着手。(もちろんこの間、進捗や品質のマネジメントもありますね)
↓
3. テスト:開発が完了したら、依頼主に受け入れテストをしてもらう。
↓
4. 納品:期待通りの動作をしているようだったら、査収完了報告書に判をもらう。
というフローが一般的かと思います。システム開発は、よく建築に例えられますが、まさにその通りです。
設計図を引いて、基礎工事をし、上棟から下地、外壁、内装工事、すべて同じ人がやり切るということはほぼあり得ません。
クラウドソーシングにおけるシステム開発の限界
では、「開発会社に”丸投げ”する」ことと「クラウドソーシングへ”丸投げ”をする」ことのもっとも大きな違いは、開発会社には各工程を担当する人が存在し、クラウドソーシングの場合は少数、または1人の受注者の場合が多いということです。
依頼側から要件を漏れ無く吸い上げるディレクターがいて、その要件から設計を行うSEがいて、その設計から開発を行うPGがいて・・・
したがって、クラウドソーシングを活用して1人で受注するためには、最低でも、以下のスキルを持ち合わせていないといけないということになります。本来は、です。
・全体をコントロールするためのマネジメントスキル
・作業を円滑に進めるためのコミュニケーションスキル
・業務の完了と開発スキル
私自身そういったスーパーエンジニアには数える程しかお会いしたことがありません。
ここが、現時点でのクラウドソーシングサービスの限界だと感じています。
クラウドソーシングが抱える問題の解決策は?
解決策としては、明確なディレクターを用意するということです。
1.あるシステム開発を依頼したい発注者がいる
↓
2.まずはディレクターをアサインする
↓
3.ディレクターが必要に応たチームをクラウドソーシングで構成し開発を進める
といった流れです。これは、ごく当たり前のことだと考えます。
この流れに合わせて、ワークスタイルに囚われないフリーディレクターの方々が増えていく、もしくはクラウドソーシング側が、そういった部分をバンドルして、差別化を図っていく進化が見られるのではないか、と思っています。
これでようやく、良質なエンジニアに対して、高すぎない単価でシステム開発を依頼できる仕組みができあがります。もしかすると、開発会社と呼ばれる企業体はどんどん少なくなっていくかも知れません。
ただし、そのためには依頼者もこの流れをしっかりと理解する必要があります。
人を減らす、工程を減らす、単純にクラウドソーシングを使えば安い人を掴まえられる、というコストカットの面だけで考えるのは危険ですので、やめておきましょう。
自分の家を立てるのと同様、そんなこと恐くてできないはずです。
クラウドソーシングが抱える問題の解決策
・フリーの優秀なディレクターに依頼する文化を形成する
・クラウドソーシング側が内部に舵取りをできるディレクターを置く
・上記のディレクターがクラウドソーシングを用いてチームを形成する
昔の話ですが、私が話をした内容に興味がある方は、お声かけいただければと思います。
















