目次 ▼
アンカーテキストを重視してる?
被リンクはSEOの重要な指標として知られていますが、発リンクに設定する「アンカーテキスト」をどれだけ重視しているでしょうか。
外部からの被リンクの数や質は意識しても、発リンクのアンカーテキストを意識する人はあまり多くないかもしれません。
ところが、発リンクのアンカーテキストもSEOに十分な効果を発揮し、検索上位表示の大切な要素になるんです。
- アンカーテキストとは何か
- アンカーテキストの正しい書き方・間違った書き方
- 内部発リンクと外部発リンクの扱いの違い
それでは早速見ていきましょう。
アンカーテキストとは
アンカーテキストとは、リンク部分に設定される文字列のことです。一般的なWEBページに設置されたリンクは、以下のように青い文字+青い下線で書かれています。
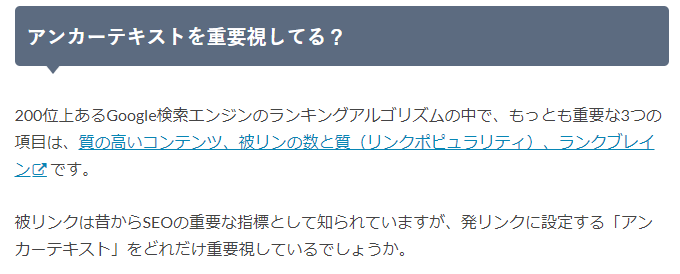
アンカーテキストは、以下のようにaタグの始まりと終わりで挟んだ部分に書かれます。
「Google検索エンジンのトップ」と書かれているため、クリックするとGoogle検索エンジンのトップページに移動すると予想できますね。
<a href="https://www.google.com/" target="_blank">Google検索エンジンのトップ</a>
アンカーテキストの書き方のポイント
リンクのアンカーテキストは、正しく書かなければいけません。正しく書くことで検索結果に影響を及ぼし、ユーザービリティを高めることができます。
アンカーテキストにはキーワードを含めた方が良い
リンクは、重要なランキングアルゴリズムの項目の1つです。つまり、Googleはページに貼られているリンクを分析しているということです。
そのため、アンカーテキストには、そのページのコンセプトになるキーワードを含めた方が評価は良くなります。
ただし、アンカーテキストにキーワードを含めた方が評価が高いという理由で、「SEO」「タイトル」などすべてのキーワードにリンクを付けるサイトを見かけますが、度が過ぎるとリンクスパムとみなされる可能性があります。
リンクに使われるアンカーテキストは、極端に同じキーワードのみを使わないようにしましょう。
リンク先ページとの関連性を示した方が良い
Googleはページのタイトルを分析して、ページの内容と高い関連性があれば良い評価をします。同じように、アンカーテキストを分析して、リンク先のコンテンツと関連性があるか判断しています。
たとえば、以下の「ページのタイトルとSEOには深い関係」というアンカーテキストのリンク先は、「titleタグとSEOの関係は?記事タイトルを最適化する書き方」というタイトルのページです。
このアンカーテキストとリンク先のページとの関連性が認められるように書くことで、評価が良くなります。一方、以下の書き方は関連性が認められないダメな書き方です。
アンカーテキストが「こちら」になっています。この場合は、「こちら」という文字列と「titleタグとSEOの関係は?記事タイトルを最適化する書き方」というタイトルの関連性があるかどうかを判断されてしまいます。
見た目でリンク先ページの内容が判断できる方が良い
ユーザーは、リンクをクリックするまでリンク先ページの内容はわかりません。
そのため、アンカーテキストを見て「ここに詳細が書いてあるのかな。」と予想してクリックした先のページがまったく違う内容だと、イラッとさせてしまいます。
イラッとしなくても、2つ、3つとリンクをクリックして、予想とまったく違う内容のページに飛ばされたら、もうそのページのリンクはクリックしなくなるでしょう。
もちろん、端的なアンカーテキストでも、リンク先が予想できなければNGです。以下のアンカーリンクは「SEO」のみです。いくらSEOをキーワードとして強調したてくても、これでは誰もクリックしてくれません。
自然な文章、自然な文字列、自然な文字数で書いた方が良い
アンカーテキストは、リンク元のコンテンツに関連性が高いほど評価が高くなり、ユーザーが内容を理解しやすいほどユーザビリティが高まります。
と言っても、以下のようにアンカーテキストが長くなりすぎることは問題です。
アンカーテキストが長くなりすぎるとユーザーの視認性が低下して、内容が理解しにくくなるだけでなく、検索エンジンもリンク先ページとの関連性を見出しにくくなります。
ただし、最適な文字数が決まっているわけではありません。文章中にリンクを含める場合は、多くても全角30-40文字に納めると、ユーザーの視認性も低下せず、Googleの判断にも悪い影響を与えないのではないかと思います。
極端な話をすると、ページ内の文章まるまるアンカーテキストにすると、キーワードスタッフィングなどのSEOスパムと認識される可能性はあります。
アンカーテキストは、あくまでも自然な文章の中で、自然な文字列、自然な文字数で書くようにしましょう。
参考リンクや引用リンクの書き方は?
上記の話から、リンクのアンカーテキストは、自然な文章の中で自然なキーワードを含み、リンク先ページの内容が理解できる書き方をしなければいけないということがわかりますね。
では、あるページを参考にしたことを示す参考リンク、あるページの文章を引用したことを示す引用リンクはどのように書けば良いのでしょうか。
引用…元の著作物を”原文のまま”利用すること
参考…元の著作物を”要約して”利用すること
参考リンクや引用リンクは、文章の中にリンクを含めるのではなく、参考箇所・引用箇所の直下、またはページ末に、出典元がわかるように明記しなければいけません。
一つの例ですが、参考リンクは以下のように記載します(文献や書籍を参考・引用した場合は、別のルールがある)。
内部発リンクと外部発リンクの扱いは変わる?
さて、リンクのアンカーテキストの書き方について話をしましたが、内部へのリンクと外部へのリンクのアンカーテキストの書き方に違いはあるのでしょうか。
ちなみに、リンクには被リンクと発リンクがあり、以下の種類に分かれます。
内部被リンク|同じドメインのページから貼られたリンク
外部発リンク|違うドメインのページに貼ったリンク
外部被リンク|同じドメインのページから貼られたリンク
アンカーテキストの書き方は内部SEO対策なので、外部に向けた発リンクはどうでも良いと思う人もいるかもしれません。ただ、基本的にアンカーテキストは、内部向けも外部向けも扱いは変わりません。
・コンテンツの信頼性が高くなる発リンク
・コンテンツの利便性が高くなる発リンク
詳しくは上記リンク先を読んで欲しいのですが、発リンクはリンク先ページとの関連性を高め、リンクすることで情報の信頼性を高め、ユーザーの利便性と満足度を増すことができます。
そのため、内部への発リンクだけでなく、外部への発リンクも同じルールで書くようにしてください。
今回を機会にして、一度サイト内のアンカーテキストを見直してみましょう。
















