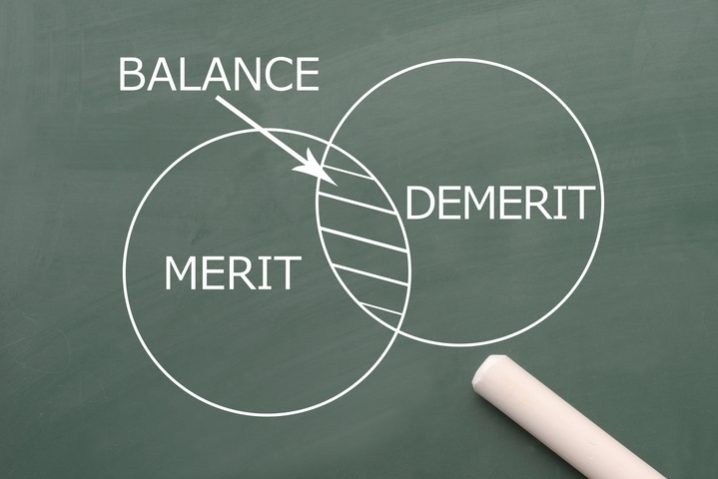目次 ▼
オウンドメディア運用を社内で提案したい
「オウンドメディアに取り組んでみたい。でも、新しいことを始めるには、上司にしっかりと説明しないといけない。」そんな悩みを抱えている人はたくさんいるでしょう。
オウンドメディアは明確な広告と違いますし、始めるためにはある程度の準備や継続するための力が必要です。
では、上司や顧客に対して、何を伝えればオウンドメディアを運用する意義をわかってもらえるでしょうか。
あなたの提案がうまくいくアピールポイントとして、オウンドメディアのメリットとデメリットをしっかりと伝えなければいけません。
今回は、オウンドメディア3つのメリット、2つのデメリットをお話したいと思います。
オウンドメディアのメリット
オウンドメディアのメリットは以下の3つ。
2.マーケティング資産の蓄積
3.見込み顧客、顧客の囲い込み
企業ブランディング、認知度の向上
オウンドメディアをうまく運用することで企業ブランディングを行えます。企業名、商品名だけではなく、企業文化や商品特徴を知ってもらうことが可能です。

これは、6月15日-7月14日の「わかること!」の数値です。30万セッションのうち、7割強の22万セッションが新規流入、残り3割弱の8万セッションが複数回このメディアに訪れていることになります。
本格的に運用しはじめて7か月ほど経ちましたが、これまでの仕事の関係者にはもちろん、新しく会う人にも「あー、知ってます。」と言われることが格段に増えてきました。
運営会社は知らなくても、わかること!を知っていてもらうだけで、話がスムーズに進むことを実感しています。
私たちの業務は、システム構築、メディアマーケティングなどが中心です。言葉にすると簡単なのですが、これだけでは何を行っている会社なのかが伝わりづらいのです。
会った人に話を聞いてもらう体制をつくるためにも、自社商品の情報やノウハウを詰め込んだメディアを持つことは非常に有意義です。
マーケティング資産の蓄積
オウンドメディアは、ユーザーに有用な情報を発信します。
ユーザーに有用だからと言って、業務に関係がない情報を流していては、オウンドメディアを運用する意味はありません。
わかること!は、比較的FacebookやSEO関連の記事が多いのですが、それは私たちが仕事に活用する情報として、調査したり、経験したりすることが多いためです。
また、これまでの業務知識の集積や、自分の考えをまとめるために情報発信する場合もありますし、内部のノウハウ蓄積のために業務で得た知識をまとめて、それを発信する場合もあります。
顧客や仕事の関係者から質問があった時に、「ここ見てもらって良いですか?」と気軽に言えるためにも必要なツールになっています。
見込み顧客、顧客の囲い込み
オウンドメディアは、いわゆるステップマーケティングを行いやすいツールになっています。
ステップマーケティングには、2ステップ、3ステップ、4ステップなどの種類がありますが、オウンドメディアを使うことによって、もう1つ進んだ「5ステップマーケティング」を行うことが可能になります。
商品やサービスに興味を示してくれるユーザーを集めること。
↓
2.見込顧客フォロー
集客によって集めたユーザーに対して、定期的に情報を送ることで、より確度の高い見込顧客に育てること。
↓
3.顧客化
見込顧客が納得して購買に結びつくこと。
↓
4.上顧客化
商品やサービスをリピートしてくれること。
↓
5.営業マン化
顧客自身が商品やサービスの良さを外部に伝えるスピーカーになってくれること。
オウンドメディアは、何を目的にするかによって目標設定方法が変わります。一例として、売上につなげるときの数字設定の考え方をあてましたので、以下を参考にしてください。
ちゃんと情報訴求をすることで、最初はなかったニーズを引き出したり、顧客自身が商品宣伝をしてくれるという目に見えづらい副次的な効果を期待することもできます。
何よりも、ここに情報を投げれば、「ある一定の人たちが見てくれる」というプラットフォームを持っていることが、企業にとって非常に大きな資産になります。
オウンドメディアのデメリット
ではその逆、オウンドメディアのデメリット、こちらは2点あります。
2.企業の情報として発信されるため、リスクマネージメントが必要
プラットフォームに成長させるまでに時間が掛かる
オウンドメディアは単純な広告と違って、ある程度の運用期間が必要なマーケティング手法です。
情報を毎日発信していても、それを受け取ってくれる人がいないと意味がありません。ある程度読んでもらえていると実感できる人数を確保しなければいけません。
どのような業種であってもやり方さえ間違えなければ1年で、これくらいは目指しても問題はないはずです。
・月間30-40万PV
・月間20-30万訪問者
ただし、しっかりとコンセプトを置き、目標を立てた上でその目標を達成するために1年、最低でも芽が出たと感じるまでに半年の期間を要します。
内部にマーケティングチームと運用チームを立てて行う場合は、その人件費と最終アウトプットの天秤です。「ニュース発信するようなもんでしょ?」という考え方が変わらない人は、絶対にやらない方が良いでしょう。
企業情報を発信するためリスクマネージメントが必要
これをデメリットと言って良いのかわかりません、当たり前のことなので。
企業体や商売、商品がコロコロと変わる会社にとっては、発信する情報が限定されますし、信頼面でのデメリットはあるかもしれません。
先ほどのようにマーケティングチーム、運用チームを立てる場合に、企業の指揮命令系統がしっかり確立されていて、発信する情報に責任が持てる人たちが担当をしていないと、炎上してしまう可能性もあります。
オウンドメディアで発信する情報のアドバイス
企業の企画部や広報部の方には、オウンドメディアのメリットとデメリットを理解したうえで、上申してもらえればと思います。
もちろん費用対効果のことも考えなければいけないので、こちらを参考にしてみてください。
最後に、発信する情報に関して簡単なアドバイスです。「リスクを怖がって、攻めていない情報を発信していても、誰も有用だとは感じません。」
たとえば、
・独自の考察や所感が入ったコンテンツ
・自社調査のデータを含んだコンテンツ
・他社に知られると真似されるかもと思うようなビジネスモデル
・業務を行う上でのコツや新しいやり方の提唱
ユーザーがメリットを感じるコンテンツは、情報発信する側がもったいないと思うくらいのノウハウを含んだ内容か、時間をかけたボリュームがある内容でなければいけません。
上司10人に見てもらうと必ず1人は反対しそうな内容、読んだ人にはメリットがあるけど自分たちにはデメリットがありそうな内容です。
このような情報にこそ、ユーザーは有用性を感じます。調べればすぐに出てくるような情報にはメリットを感じません。
すべてが攻めのコンテンツである必要はありませんが、せめて10本中1-2本は攻めの情報を出して、独自性をアピールしていきたいです。このあたりも上司を説得する必要があるところですね。